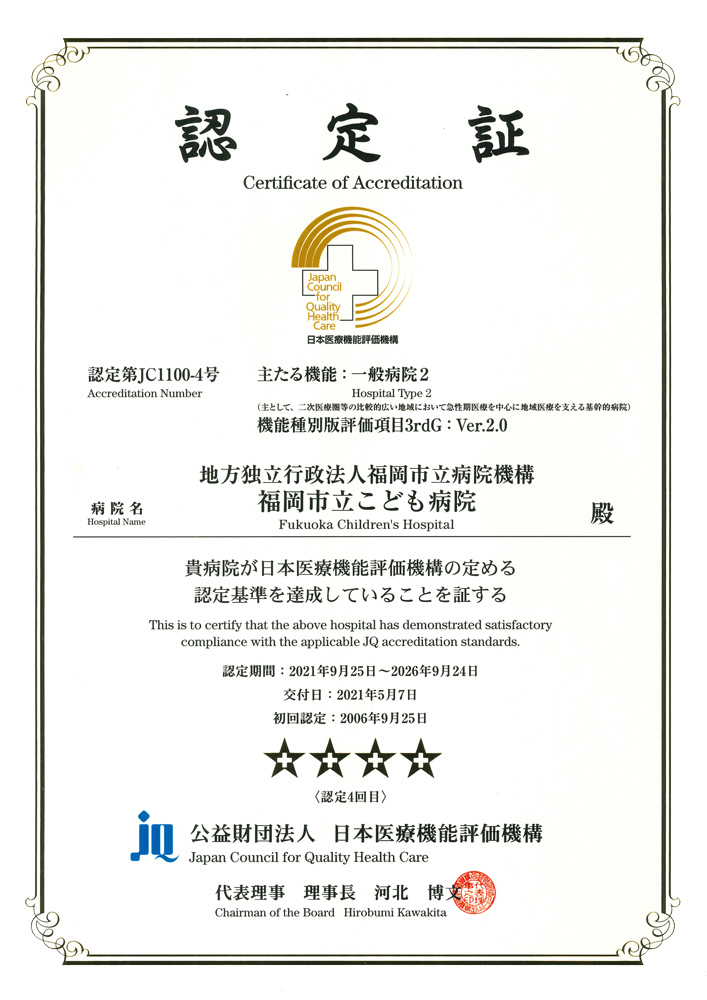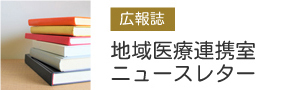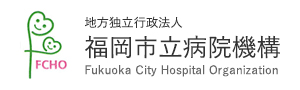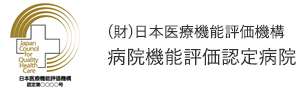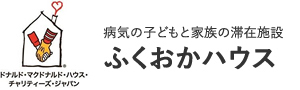入院基本料について
当院では、1日の入院患者人数に対する看護職員を以下の通り配置し、交代で24時間看護を行っています。なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。また、病棟ごとの配置人数は、病棟に掲示しております。
急性期一般入院料1
入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
小児入院医療管理料1
入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
新生児特定集中治療室管理料1
入院患者3人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
DPC対象病院について
当院は入院医療費を、患者様の病名や診療内容に応じた包括評価と出来高評価を組み合わせて算定する「DPC対象病院」となっております。
医療機関別係数1.4446(基礎係数1.0451+機能評価係数Ⅰ0.3307+機能評価係数Ⅱ0.0682+救急補正係数0.0006)
入院食事療養費
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時・適温で(夕食については18時以降)提供しています。
明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診 療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行いたします。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用を推奨しております。
マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いします。
なお、令和6年12月より、医療情報取得加算として下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。
| 初診時(月に1回) | 1点 |
| 再診時(3か月に1回) | 1点 |
一般名処方について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要なお薬が提供しやすくなります。
情報通信機器を用いた診療について
当院では、情報通信機器を用いた診療の初診の場合に向精神薬の処方はいたしません。
ハイリスク分娩管理加算に係る院内掲示
分娩件数(令和6年1月~12月) 297件 産科医師 6名 助産師25名
コンタクトレンズ検査料について
別添の「コンタクトレンズ検査料の診療費について」【PDF】をご参照ください。
院内トリアージ実施料について
別添の「トリアージの実施について」【PDF】をご参照ください。
医療DX推進体制整備加算について
別添の「医療DX推進体制整備加算について」【PDF】をご参照ください。
病院(医療関連)感染対策指針
Ⅰ.病院(医療関連)感染対策指針の目的
この指針は、福岡市立こども病院(以下「当院」という)における感染防止対策及び院内感染発生時の対応等において、感染
管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的として定めるものである。
Ⅱ.院内(医療関連)感染対策に関する基本的な考え方
1.標準予防策及び感染経路別対策の遵守 患者の感染症の有無に関わらず、すべての患者の血液、体液、汗を除く排泄物(糞
便、尿、嘔吐物、喀痰など)、損傷した皮膚、粘膜には感染性があるとみなすという標準予防策を厳格に遵守する。 標準
予防策に基づき湿性生体物質を取り扱う場合は、必要に応じて手指衛生を実施し、未滅菌手袋、プラスチックエプロン、
マスク、ゴーグル等を着用する。 また、患者の感染症が判明している場合、その感染経路に基づく感染経路別対策(接
触予防策、飛沫予防策、空気予防策)を標準予防策に追加して実施する。
2.院内(医療関連)感染発生時の原因究明、感染拡大防止、個々の感染症症例治療、再発防止。
院内(医療関連)感染が発覚した場合、直ちに以下の対策を効率良く実行する。
(1)感染源特定のため現場での情報収集
(2)現場に従事するスタッフや部署環境における微生物学的調査
(3)標準予防策と感染経路別感染対策の遵守状況の確認
(4)感染対策に関する助言。
(5)適正な抗菌薬投与、隔離対策・隔離予防、消毒薬使用などについての指導
(6)感染症患者の治療や移動及び退院に関する助言
(7)情報収集、調査により推定される院内感染の原因についての協議
(8)院内(医療関連)感染アウトブレイク発生時の対応・終息の判断と終息宣言
(9)院内(医療関連)感染事例の総括と当該部署への再発防止に向けた提言
Ⅲ.院内(医療関連)感染対策のための委員会その他の組織に関する基本事項
当院における院内(医療関連)感染防止策を推進する管理体制は以下のとおりとする。
1.感染対策委員会(Infection Control Committee:以下ICC)
(1)病院長の諮問に応じて種々の院内感染を予防するとともに、発生した感染症の拡大防 止と制圧・終息を図ることを目
的として設置する。
(2)感染対策に関する情報を把握し、感染制御チーム(Infection Control Team以下「ICT」 という)と抗菌薬適正使用支
援チーム(Antimicrobial Stewardship Team以下「AST」 という)の活動に対する助言、援助を行う。
(3)感染対策に関連する事項の決裁を行う。
(4)委員会は毎月1回開催する。必要な場合には、委員会委員長は臨時委員会を開催する。
2.感染対策室
(1)病院全体の感染対策について組織横断的に管理する。
(2)ICTとASTの事務局機能をもつ。
3.感染制御チーム:ICT
(1)感染対策部門として感染防止対策を適切に実践するために設置する。
(2)ICC・感染対策室の指示のもと、感染対策推進の中心的な役割を担う。
4.抗菌薬適正使用支援チーム:AST
(1)ICC・感染対策室の指示のもと、抗菌薬の適切な使用により薬剤耐性菌の出現を防止するとともに感染症患者の治療が
円滑に行われるための活動を行う。
5.感染リンクスタッフ
(1)ICT方針の下、各職場における感染対策の実践モデルとなり感染対策を推進する。
Ⅳ.院内(医療関連)感染対策に関する職員研修についての基本方針
1.感染対策の基本的な考え方及び方策について、職員への周知を目的に実施する。
2.研修会は、新規就職時に1回、全職員を対象に年2回開催する。また、必要に応じて職種別・部署別に研修会を開催する。
3.研修会開催に際し、研修内容及び参加実績記録を保存する。
Ⅴ.院内(医療関連)感染発生時の対応に関する基本事項
1.疫学的・臨床的問題となる感染症を患者が発生した時、または、感染の恐れがある時は感染対策室・ICTに報告すると共
に、直ちに必要な対策を講じ実行する。
2.感染対策室・ICTは、サーベイランスデータ注1)、院内ラウンド等からリスク事例を把握し、職員へフィードバックし適
切の感染対策の支援をする。
3.ASTは、感染症例報告、血液培養陽性例、広域抗菌薬届出報告、抗菌薬長期使用症例、抗菌薬処方状況の把握等を検討し
診療の支援をする。
4.院内での対応が困難な事態が発生した場合や、その発生が疑われる場合は、地域の専門家等に相談する体制を確保する。
5.感染症法に基づいて感染症を診断した場合は、診断した医師は速やかに届出を行う。
Ⅵ.患者等への情報提供と説明
1.本指針は、病院ホームページにおいて公開し、患者及び家族が閲覧できるものとする。
2. 疾病の説明と共に、感染防止の基本について患者等へ説明し理解を得た上で協力を求める。
3.本指針は、病院電子カルテ及び院内Webを通じて全職員が閲覧できるようにする。
Ⅶ.病院における院内(医療関連)感染対策推進のために必要な事項
1. 院内(医療関連)感染対策マニュアルを整備し、職員はマニュアルを遵守し業務中の感染対 策に努める。
2.院内(医療関連)感染対策マニュアルは、科学的根拠と医療上の安全性・経済性を考慮しつつ、最新の知見に基づき適切に
改訂を行う。
3.院内(医療関連)感染対策マニュアルは全職員に周知する。マニュアルは定期的に見直し、変更時は全職員へ周知徹底を図
る。
4.職員は自らの健康状態を把握し、保持に努める。
Ⅷ.用語の解説
注1)サーベイランスデータとは、感染症の動向把握や感染対策の効果を判定する情報です。サーベイランスデータを活用し、
院内で発生している感染症を早期に察知し対応します。
附 則
この指針は、平成26年11月1日から施行する
令和2年10月20日改訂
令和7年 8月12日改訂