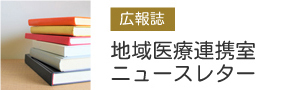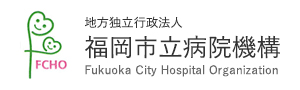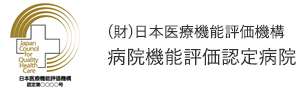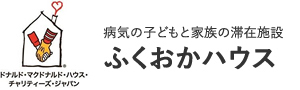先輩インタビュー
先輩へのインタビュー01
1.看護師を目指したきっかけは?
元々人と関わる仕事がしたいと考えていて、医療系のドラマも大好きで興味を持っていました。そんな中で高校生の時に参加した病院での職業体験で、患者さんに親身になって対応している看護師に強い憧れを抱き、自分もこの職業に就きたいと思ったのがきっかけです。

2.小児看護を選んだ理由は?

理由は大きく2つあります。1つ目は、進路を決めるにあたって、子どもが大好きだったため看護師と保育士で迷っている時に、小児看護の道に進み、医療に携わりながら子どもに関わりたいと思ったからです。2つ目は、大学時代の実習での小児領域、母性領域の実習の経験で小さな命の生命力に感動し、自分も関わりたいと思ったからです。
3.入職後の教育体制について教えて下さい。
入職してから2週間は、新卒全員で基本的な看護技術や社会人としての接遇などを学びます。2週間経つと集合研修の最初に実施される面談を加味して決定された配属先へとそれぞれ移り、そこで研修や教育を受けます。GCUでは、看護技術に関しては手順書を用いて確認した後、見学→実施→自立チェックの順番で手技を練習するため、自分一人で実施する時には注意点や手技を確実に獲得できているという自信がついていました。また、実地指導者でもある看護師がいるため、不安なことや勉強でサポートを受けられる他、ポートフォリオという振り返り用紙を用いて、ペア看護師と業務の振り返りを行い、良かった点や課題を明確にしていきながら経験を積んでいくことができました。

先輩へのインタビュー02
1.PICUの魅力はどのような所ですか?

手術直後の患者さんが多く、呼吸や循環など全身管理が学べるところが魅力です。また、1人の看護師が1~2人程度の患者さんを看るため、一人ひとりじっくり関わることができる点も魅力だと感じています。患者さんが手術直後から徐々に回復し、笑顔が見られたり食事ができるようになっていく過程をそばでみられる点も魅力だと思います。
2.集中系部署の雰囲気について教えて下さい。
重症な患者さんも多く、緊急を要することや厳しい状況に直面することも多々あります。そんな中でも、熱心に教育してくれる先輩がいて、近くに医師がいる時間も多い為、分からないことはすぐに共有し学び合う雰囲気があります。また、PNSを取り入れている為、ペアの看護師と相談しながら看護が出来る安心感もあります。看護師一人ひとり意識が高く、子どもの為に自分にできることを考えながら日々看護しています。

3.仕事と家庭や育児の両立について教えて下さい。

自分のこどもが生まれた直後は育児休業を取得し、こどもの成長を感じながら家事と育児に専念する時間が取れました。現在は復帰し、夜勤もある中で奥さんにお願いすることも多いですが、協力しながら楽しく育児をしています。PICUは定時に退勤ができる事も多い為、家庭との両立もしやすくなっていると感じています。また、先輩ママ、先輩パパも多くいるため、時にはアドバイスを貰いながら家庭との両立を頑張っています。
4. 休日はどのように過ごしていますか?
家族全員アウトドア派なので、休みがあれば家族みんなで外出して過ごしています。旅行も好きでよくいろんな所へ行ってリフレッシュしています。また、仲の良い同期や同僚と食事に行くことも多く、家族ぐるみで出かけることもあります。仕事での悩みや私生活の事まで何でも相談しています。
先輩へのインタビュー03
1.手術室看護師ってどのようなお仕事ですか?
子どもの安全を最優先に考え、手術がスムーズに進行するように看護を行っています。また、手術はチームで行うため、外科医や麻酔科医などと連携して密にコミュニケーションを取っています。手術は子どもやご家族にとって特別であり、手術に対する不安を抱えていることが多いです。そのため、不安を和らげ、安心感を提供できるような関りを心掛けています。

2.やりがいを感じるときは?
外科医・麻酔科医・看護師等と連携し、同じ目標に向かってチーム一丸となって動き、手術が終了し、子どもが無事に家族のもとへ戻った時に、安堵感とやりがいを感じます。また、手術前の緊張や不安の中で、手術室に一人で入室し、頑張る姿や手術後の子どものやり切った表情や手術前には見られなかった笑顔、「ありがとう。」と感謝の言葉に大きなやりがいを感じ、自分の励みとなります。
3.自分自身の成長を感じたときは?

緊急時でも、少しずつ冷静に対応が出来る様になった事、外科医や先輩看護師より褒められるなど評価してもらった際に、自分の成長を感じます。 また、チーム内で自分が信頼されて仕事を任せて貰える事にも成長を感じています。
4.今までの経験の中で特に印象に残っているエピソードはありますか?
小学校低学年から何度も手術をされている患者さんを、1年目より担当させて頂き、私が6・7年目の際に最後の手術を終えられました。長年にわたり継続して看護をさせて頂けたこと、ご家族からのお話、お子さんの思いの変化など沢山の事を学びました。手術室という短時間の関りの中でも、私のことを認識し、名前を覚えて呼んで貰えた事が初めてで大切な思い出です。
5.手術室ナースからのメッセージをお願いします。
手術室は閉鎖的で、子どもと直接関わる機会が少ないという印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、麻酔によって子どもが眠っている状態だからこそ、看護師は子どもの代弁者として、安全に尊厳を守るために看護を担っています。手術室での看護は、技術的なスキルや知識も求められますが、直接コミュニケーションを取る機会が少ないからこそ、手術室にしかない看護があり、そこを忘れずに大切にしたいと思っています。

先輩へのインタビュー04
1.仕事内容とやりがいについて教えて下さい。
総合診療科、アレルギー・呼吸器科、小児感染・免疫科の混合病棟で勤務しています。食物アレルギー等の検査入院や歯科治療などの予定入院に加え、救急病棟として熱性痙攣や気管支喘息、川崎病等、昼夜問わず入院を受け入れています。突然の入院で不安な子どもやご家族へ安心できるような声掛けを行い、多職種と協働しながら看護を提供しています。子どもが笑顔で退院していく姿を見ると頑張って良かったと感じます。
2.後輩にはどのような関りをしていますか?

入職1年目の頃は、なかなか自分の意見や考えを先輩に伝えることができませんでした。実地指導者となった今現在は、その経験を活かし、後輩が考えや意見を伝えやすいように関わることを心掛け、後輩のサポートに努めています。どのように説明したら後輩が理解しやすいのか、院内外の研修で学び、私自身日々考えながら指導を行っています。難しさは感じますが、後輩の成長した姿を見ると嬉しく思います。
3.今までの経験の中で特に印象に残っているエピソードはありますか?
退院後も自宅で医療的ケアが必要になったこどもやご家族との関わりの中で、私達が考えている以上にご家族の不安が大きいことを知りました。そこで入院中は、こどもとご家族のために何ができるのか考え、退院後の生活を見据えながらケアを行いました。そして退院後も切れ目なくケアが提供できるよう、医療者とご家族だけではなく、退院後も連携を取る機関と共に退院支援カンファレンスを行い、ご家族の不安の軽減に取り組みました。退院する際ご家族に「ここに入院して良かったです。不安もあります。でも、家に帰れないかもしれないと思っていたのが、家に帰って家族とみんなで過ごせると思うと嬉しくて感謝しかありません。」と言ってもらった時には、頑張って良かったと感じました。

4.リフレッシュ方法について教えて下さい。
職場の先輩や後輩、同期、友人と食事に行ったり、旅行に行ったりすることです。1年目の頃に一緒に頑張ってきた同期とは、今でも関わりがあってこの縁は一生の宝物だと感じます。
先輩へのインタビュー05
1.小児看護専門看護師の役割と活動について教えて下さい。

小児看護専門看護師は、子どもたちが健やかに成長・発達していけるように療養生活を支援し、看護師や医師、薬剤師、管理栄養士、保育士などさまざまな職種のスタッフと連携して、質の高い看護の提供を目指しています。また、入院中の子どもやご家族、看護師が抱える課題について、少しでも解決できるよう、専門看護師の6つの役割機能(実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究)を発揮しながら、活動を行っています。私のサブスペシャリティは、慢性期にある子どもとご家族への看護で、特に、アレルギー疾患のある子どもと家族への療養支援に携わっています。医師と協働しながら、2021年よりアレルギー看護専門外来を開設しました。
2.小児看護専門看護師を目指したきっかけを教えて下さい。
私が看護学生時代には、看護倫理を学問として体系的に学ぶ機会がなかったため、いつも「これでよかったのだろうか」という疑問が残っていました。そのような中で、子どもの治療方針をめぐり、子ども自身やご家族とのかかわりを通して、意思決定支援の重要性を実感しました。臨床現場で実践していく中で、さまざまな障壁に突き当たることが多く、少しでも問題解決の糸口を見つけたい、そして、子どもの成長発達や専門的知識・スキルを習得したいと思い、大学院に進学し、資格取得を目指しました。
3.現在はアレルギー看護専門外来の小児アレルギーエデュケーターとしてどのような活動をしていますか?
小児アレルギーエデュケーターとは、日本小児臨床アレルギー学会資格で、アレルギー疾患のある患者を対象に専門的に指導を行っています。私は、小児看護専門看護師と小児アレルギーエデュケーターの資格を活かして、アレルギー看護専門外来を行っています。外来では、医師の診断、説明後に病気の理解を支援したり、子どもの発達段階に応じた疾患や治療の説明を行っています。喘息の治療で使用する吸入器の使い方、アトピー性皮膚炎治療でのスキンケア方法、食物アレルギーの症状への対応、アドレナリン自己注射(エピペン®)の使用方法について説明をしています。また、家族が抱える不安な思いに寄り添いながら、治療が継続できるような支援をしています。

4.こども病院の教育体制について教えて下さい。
看護師一人ひとりが自分の持っている力を発揮しながら、キャリア開発に主体的に取り組みながら、看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)に沿って、専門職業人として自律した行動がとれるよう、経験を積み重ねています。自分の次のキャリアを考える際には、専門看護師や認定看護師、診療看護師など資格取得を目指すことも可能です。小児看護専門看護師は、院内の教育委員会や倫理委員会に所属し、スタッフの育成を支援しています。そのひとつに、看護研究研修を企画運営し、初めて看護研究に取り組む看護師を指導し、院内発表を経て、関連学会で発表に至るまでを支援しています。また、将来、専門看護師の資格取得を目指している大学院生の実習指導者として、大学教員と連携を図りながら、実習を受け入れています。