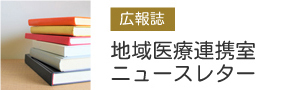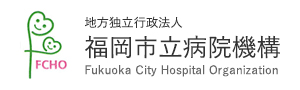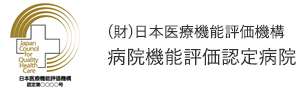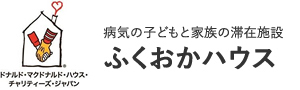形成外科
- 当科について
-
診療内容
形成外科は全身の体表や皮下の疾患を機能的、整容的に治療します。先天異常に対する治療は保険適応です。お子さんやご家族が安心できるような質の高い医療を提供していきたいと考えております。お悩みのことがありましたら是非、一度ご相談下さい。
科の特徴・特色
形成外科は「形と機能を創る」医学です。形成外科で扱う疾患はたいへん幅広く、内容も多彩です。外観の変形、醜形はそれが些細なものに見えても、機能的、整容的に大きな悩みとなり、お子さんやご家族の大きな負担になっていることが少なくありません。形成外科ではお子さんやご家族と話し合いながら、あらゆる手法や特殊な技術を駆使し機能的、形態的にできるかぎり正常に近づけることによって悩みを解消し、笑顔を取り戻して頂くことを目標としています。手術痕や外傷を皮膚外科、創傷外科のプロとして可能な限りきれいに治すことを目指しています。 必要に応じて院内他科や他施設(福岡大学病院など)と連携をとって、患者さんの診療にあたります。
診療科より
外来診療時間は、月・火曜日が13時~16時、木・金曜日が9時30分~12時30分です。
診療は予約制になっております。予約は、お電話、LINEまたは外来窓口で承ります。外傷などの急患は、できる限り対応いたします。お電話でご連絡下さい。ただし、手術中などで対応できない場合もあります。
月・火曜日 13時~16時 木・金曜日 9時30分~12時30分 急患、受診を急ぐ場合には上記の限りではありません。まずは担当医あてに電話で御相談下さい。
- 主な対象疾患
-
主な対象疾患
頭の変形
頭蓋骨早期癒合症、短頭、舟状頭、斜頭、三角頭、尖頭など。 「頭の形がおかしい」と受診する児の多くは位置的頭蓋変形症、いわゆる寝ぐせです。しかし、その中に非常に稀ながら頭蓋骨早期癒合症が紛れ込んでいます。手術を行った方がよい症例に対しては脳神経外科などと一緒に手術による治療を行います。手術は必要ないけれど、今より頭の形をよくしたいと希望される方には連携している福岡大学病院でのヘルメット治療をお勧めしています。
くちびるの先天異常
唇顎口蓋裂、唇裂、唇顎裂、口蓋裂、粘膜下口蓋裂、巨口症など。 先天性外表奇形の中では最も頻度が高い疾患の一つです。生後3か月~9か月頃に口唇形成術、生後1歳~2歳頃に口蓋形成術を行います。その後も耳鼻科による中耳炎の管理、言語聴覚士による言語の訓練、歯科による咬合の管理などを経て8~10才頃に顎裂部骨移植を行います。
チーム医療で患児の成長発達の評価、管理を行い治療至適時期に手術を行っています。
耳の変形
小耳症、埋没耳、折れ耳、立ち耳、副耳、耳瘻孔など。 小耳症は組織の不足が原因となっており、10才前後に肋軟骨による耳介の形成を行います。耳介を作る手術と耳介をおこす手術で少なくとも2回の手術が必要となります。埋没耳は耳介軟骨が皮下に埋没しており、マスクや眼鏡の装着が困難となります。以前は就学前に手術を行っていましたが、コロナ禍でマスクをかけ始める年齢が低年齢化していることもあり、手術時期も早まる傾向にあります。
副耳、耳瘻孔は頻度が高い疾患です。いずれも1歳以降に手術を行います。
まぶたの変形
眼瞼下垂症、眼瞼内反症、霰粒腫など。 先天性眼瞼下垂症ではまぶたをもちあげる上眼瞼挙筋の機能が生まれつき低下しているため、眉毛や顎を挙げて前を見ようとします。重度の眼瞼下垂による廃用性弱視がなければ4才頃に挙筋前転術や筋膜移植術での治療を行います。眼瞼内反症は内反した睫毛により角膜が傷つき、眼脂、掻痒、疼痛、羞明などの症状が生じます。睫毛近くを切開して、睫毛の向きを変える手術を行います。
体幹、手足の変形
漏斗胸、鳩胸、ポーランド症候群、臍ヘルニア、副乳、腋臭症、絞扼輪症候群など。 漏斗胸は最も頻度の高い先天性胸郭変形であり前胸壁が漏斗状に陥没している状態です。動悸、不整脈、呼吸障害といった心肺機能の異常を呈することは意外に少ない。6~10才頃にNuss法により治療を行います。術後3か月程で通常の日常生活が行えるようになり、バーの留置期間は約3年です。鳩胸は前胸壁が前方に突出した胸壁変形でNuss法に準じた考え方で金属バーを挿入することがあります。
臍ヘルニアは2才以降にはそれ以上の改善が難しくなるため、手術を行います。
褥瘡
患児を中心に医師、看護師、リハビリ、栄養士、薬剤師と多職種によるチーム医療が重要です。特に小児の場合は褥瘡があることにより生活の質が大きく低下します。患児それぞれの病態(活動性、栄養状態、局所の状態)に合わせて目指す目標を決めます。目標に向かって適切な軟膏、創傷被覆材による保存的治療、根治を目指した手術を組み合わせ治療していきます。
血管腫、血管奇形
乳児血管腫、毛細血管奇形、静脈奇形、リンパ管奇形など。 乳児血管腫(いわゆる苺状血管腫)は自然退縮するとはいえ、大きいものでは瘢痕になる場合があります。症状によって色素レーザー治療や内服治療(プロプラノロール)の適応を判断し、必要に応じて治療を開始します。毛細血管奇形(いわゆる単純性血管腫)は、生下時からみられ自然消褪しませんが、皮膚の厚さが加齢に伴って厚くなるため褪色する場合もあります。しかし、反対に色がこくなったり、腫瘤を形成する場合もあります。静脈奇形、リンパ管奇形では生じた部位による症状と経過を見ながら硬化療法や手術療法の適応と至適時期を判断していきます。
腫瘍
色素性母斑、表皮母斑、脂腺母斑、皮様嚢腫、石灰化上皮腫、頚部嚢胞、脂肪腫など。 いわゆるほくろでは小さいものは単純に切除し、傷痕をきれいにすることを目標にします。大きいものでは組織拡張器の挿入や植皮術、皮弁術が必要になる場合があります。当院では必要に応じて培養表皮による治療も行っています。頭部脂腺母斑は頭髪を欠く黄褐色の平坦な局面として見られることが多いです。頻度は高くないが将来的に悪性腫瘍を生じる可能性もあると言われています。
外傷、熱傷
挫創、切創、第1~3度熱傷、など。 皮膚の損傷以外に骨、関節、筋、靭帯、神経、血管の損傷がないかの診断が必要となります。外傷、熱傷はできる限り瘢痕をきれいにするため、受傷早期に適切な加療が必要です。介入時期が遅くなると治療はより困難になります。
- 診療実績
-
診療実績(2023年度)
年間外来患者数 3,519名 年間手術件数 317症例
- 医師紹介
-
医師紹介
名前 森田 愛(Ai Morita) 専門分野 形成外科全般 所属学会 日本形成外科学会
日本創傷外科学会
日本口蓋裂学会
日本フットケア・足病医学会
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
日本抗加齢医学会
日本美容外科学会
日本シミュレーション外科学会主な資格等 日本形成外科学会領域指導医
形成外科専門医
創傷外科学会専門医
日本抗加齢医学会専門医
小児形成外科分野指導医
再建・マイクロサージャリー分野指導医
身体障害者指定医
小児慢性特定疾病指定医
臨床研修指導医
緩和ケア研修修了
オンライン診療研修終了名前 伴 楓子(Huuko Ban) 専門分野 腫瘍外科 レーザー 所属学会 日本形成外科学会
日本創傷外科学会
日本熱傷学会
日本美容外科学会名前 星子 周平(Shuhei Hoshiko) 所属学会 日本形成外科学会
- 役立つ情報のリンク
-
役立つ情報のリンク